第一蹠骨とは足の第一趾(親指)のことです。
足の第一趾を使って動きが悪い骨盤に動きの幅をつけるやり方があります。
右の骨盤が下がっている人、あるいは左の骨盤が開いている人は体重が足の親指に乗りません。
常に踵側から小指側にかかっています。
歩くときも小指側に体重がかかり、親指に乗りません。
第一蹠骨(しょこつ)親指のつけ根付近が固まっています。
このつけ根に付着しているコリを捉えて、骨盤を調整するやり方をお話しします。
第一蹠骨の捉え方
第一蹠骨で捉える箇所は、親指の中足骨の窪み付近です。
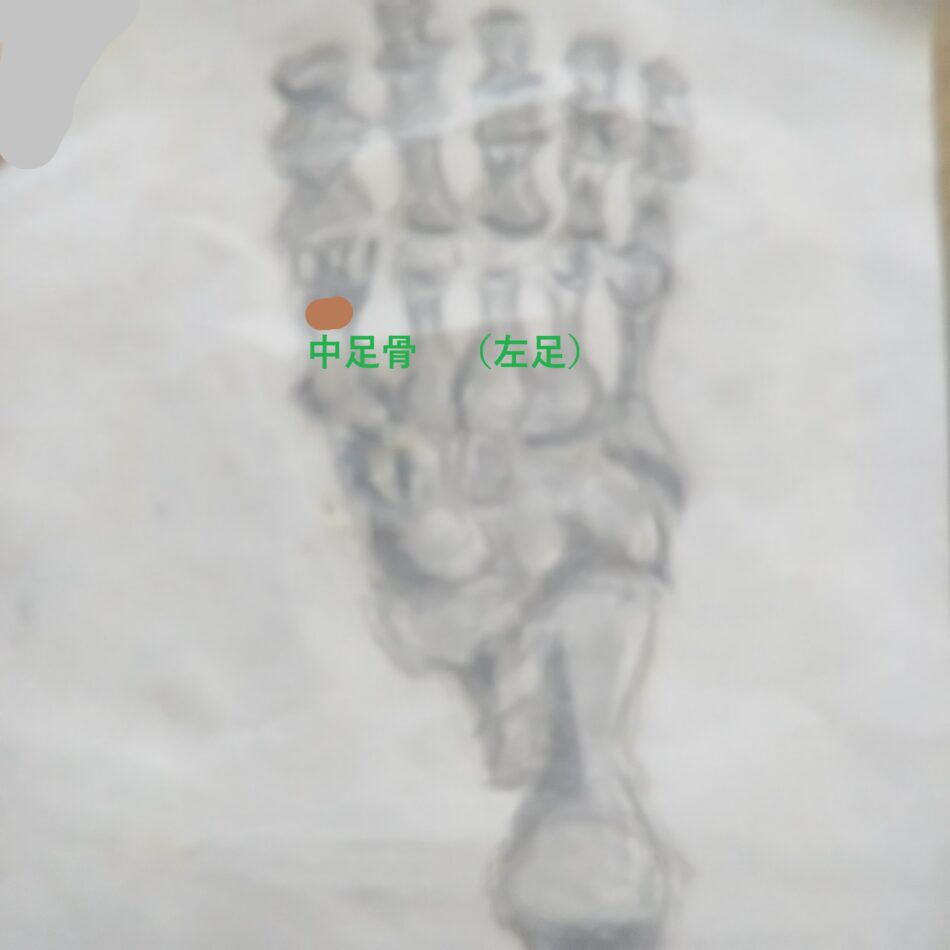
絵は左足の裏ですが、マークをつけている付近を捉えます。
その付近にコリがついているので、柔らかく捉えることで動きが悪い方の骨盤に動きの幅がつきます。
右の骨盤は前後に動くので、上下の方向に動かし、左の骨盤は左右開閉に動くので内線させるように動かします。
整体 操法でも述べているように手の力を抜くことです。
手の力で行えば、相手の体は変化しません。
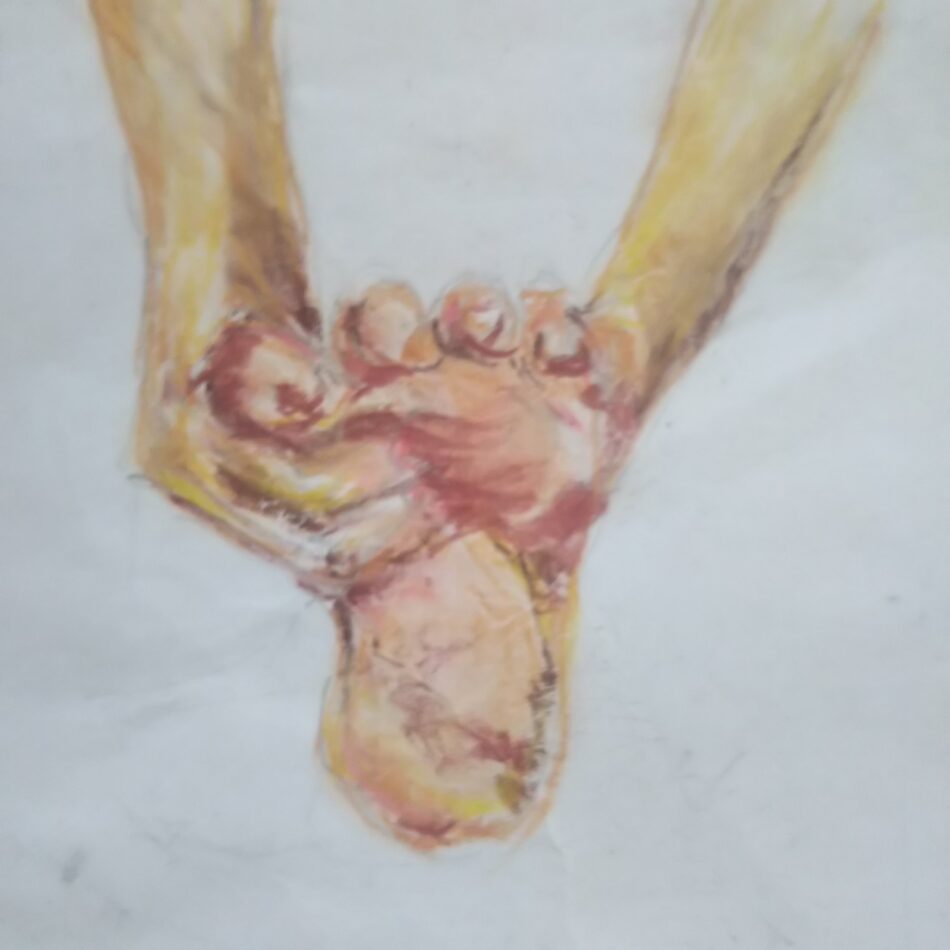
第一蹠骨の調整は骨盤調整の基本
右の骨盤が下がって動きの幅がなくなっているとき、左の骨盤が開いて動きの幅がなくなっているときは、腰痛が起きたり膝に痛みが起きます。
第一蹠骨と骨盤の弾力がなくなっていると、腰椎の弾力がなくなったり、膝に正しく体重が乗らなかったりするからです。
私共の整体では腰痛や膝痛が起きているときは、第一蹠骨を介しての骨盤調整を必ず行います。
骨盤の調整は第一蹠骨だけでなく、他にもやり方があります。
今後、骨盤の調整もお話しします。
人間と猿の大きな違いの一つに第一蹠骨(しょこつ)の発達があります。
人間が片足で立つことができるのは、足の親指である蹠骨(しょこつ)に力が入り、親指と小指と踵で立つことができるからです。
また蹠骨が発達したことで人間の脳も発達したと言われます。
昼に活動しているとき、ものごとに集中できる人は左足の蹠骨に力がかかり左の骨盤が引き締まり、左の腰椎4番が緊張しています。
反対にうつや認知を抱えている人は、左足の蹠骨に力が入らず左の骨盤が開いて腰椎4番が弛んでいます。
左足の蹠骨に力が入らず骨盤が開いているときは、脳に上がる血行が滞ります。
このように脳の血行は、蹠骨と骨盤の状態に影響されると言えます。
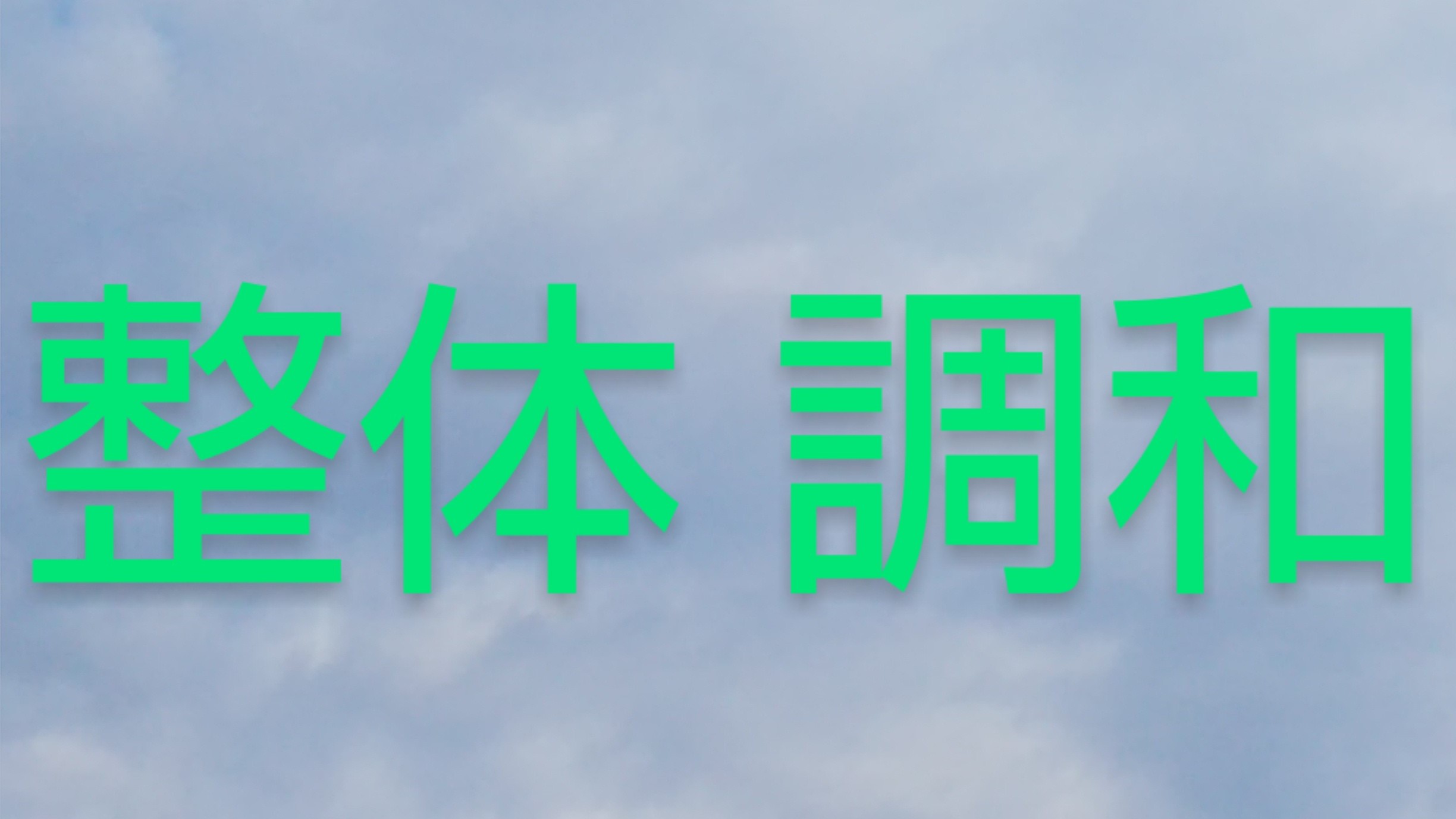



コメント