頸椎は胸椎・腰椎と同様に体の中の状態が表面に現れます。
異常があれば、コリが頸椎の表面に現れます。
頸椎を正しく観察して表面のコリを見つけると、相手の健康状態が見えてきます。
頸椎にも調整する箇所がいろいろありますが、脳に通じる神経や血管が走行しているので、丁寧に扱わなければなりません。
指に力が入ってゴリゴリ押すようなことをすると、揉み返しが起きて受けた相手は気分が悪くなることがあるからです。
もちろん、頸椎以外でも雑に扱って良い箇所などありませんが、特に慎重に扱わなければならないことを心得てください。
丁寧に調整することにより、いろいろな不調が快方に向かいます。
あくまでも愉氣を主体にする
整体では骨格矯正のように首を鳴らすようなことはしません。
柔らかく触れ、愉氣を主体にして調整します。
それで相手は十分変わります。
頸椎1番
頸椎1番は後頭骨の下に入っているため、直接触れることは出来ません。
後頭骨を介して、調整します。
相手に座ってもらい、術者は後ろで蹲踞で構えます。
親指を後頭骨に当て、残りの指4本は耳を塞がないようにし、下の小指は喉に当てないようにし、指先に神経を集中します。
手の力を抜いていると左右の後頭骨のどちらかの下にブヨーとするコリが付着していることがわかります。
そのコリがあるほうの頸椎1番の異常です。
また左の骨盤が開いているときは、左の後頭骨が下がりコリが付着しています。
右の骨盤が下がっているときは、右の後頭骨が下がりコリが付着しています。
左右のどちらに異常があるか確認できたら、コリが付着している方の後頭骨に柔らかく親指を当て、反対の手は額に手を当てます。
角度を上に向け、下半身から触れている親指に力を伝え、額に当てている手で顎が上がるように対応すると親指に力が集まります。
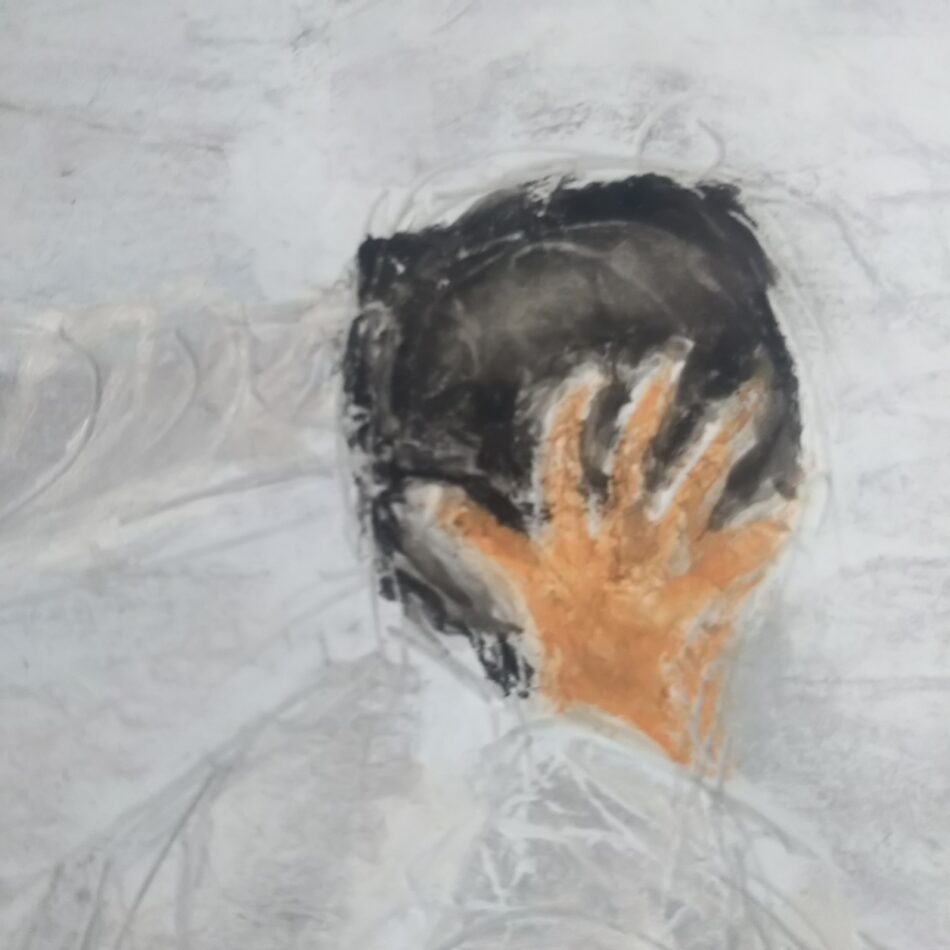
頸椎2番と3番の観察と調整
相手の姿勢と術者の構えは頸椎1番と同じです。
相手には軽く顎を上げてもらい、柔らかく触れて後頭骨のすぐ下にある棘突起を確認します。
そこが頸椎2番で左右を比べて硬直している方が異常です。
頸椎2番を確認したら、両手の親指を頸椎2番に当て、残りの指4本で相手の頬を包みます。
手の位置が決まれば、相手の顎が上がる形で腰から親指に力を伝えます。
耳と目を塞いだり、小指で喉を圧迫しないように注意しましょう。

頸椎4番と5番の観察と調整
相手は座位で術者は蹲踞で行います。
頸椎4番は頸椎の真ん中辺り(頸椎5番は4番の一つ下)です。
柔らかく触れ左右どちらかの硬直を見つけたら、親指以外の指4本で相手の頬を包み親指を硬直している頸椎に当て、腰から前方に力を伝えます。
頸椎2番と3番と同様に小指が相手の喉を圧迫しないように注意しましょう。

胸椎6番と7番の観察と調整
相手は座位で術者は膝立ちで行います。
首を前に倒してたとき飛び出している椎骨が頸椎7番(頸椎6番は7番の一つ上)です。
相手には首を前に倒してもらったまま、左右のどちらが硬直しているかを確認します。
硬直している箇所が異常です。
硬直を確認したら、親指を硬直に当て残りの指4本は頬を柔らかく包みます。
頸椎6番と7番も小指で喉を圧迫しないようにしましょう。
腕の力ではなく体全体を使い、親指が斜め下に圧がかかるようにします。

仰向けでの頸椎の調整

なぜ 花粉症が発生するか?で述べている頸椎2番と3番の一側を調整するとき、環椎(頸椎1番)と軸椎(頸椎2番)の一側と二側を調整するときは、相手を仰向けにして頸椎を調することがあります。
相手を寝かせ、上方に蹲踞で構えます。
一側及び二側に中指を当て、付着している硬直を探します(手の力を抜いて練習したらわかるようになる)。
硬直が異常個所です。
柔らかく捉えると硬直が弛み、花粉症をはじめ頸椎1番と2番の不調が快方に向かいます。
頸椎を調整したあとは、下頚(かけい)の調整を行いましょう。
下頚調整

頸椎を調整した後は脳内の血行が乱れ、頭痛や気分が悪くなることがあります。
頸椎の調整後は必ずこの下頚調整を行います。
相手に正座で座ってもらい、背後から両方の肩を包み親指を肩甲骨と鎖骨の間に当てます。
柔らかく触れていると親指を当てている箇所が弛んで窪みができます。
手の力を使わず膝を曲げて沈み込むように体を下げると、窪みがさらに弛んで親指が入ります。
親指が割れ目の底に当たれば硬直を感じるので、ポンと素早く力を抜きます。
首と肩のコリ・腕の疲労・内臓の不調・呼吸器の不調・背骨の二側の緊張が弛みます。
二宮整体ではあらゆる症状において、調整する箇所です。
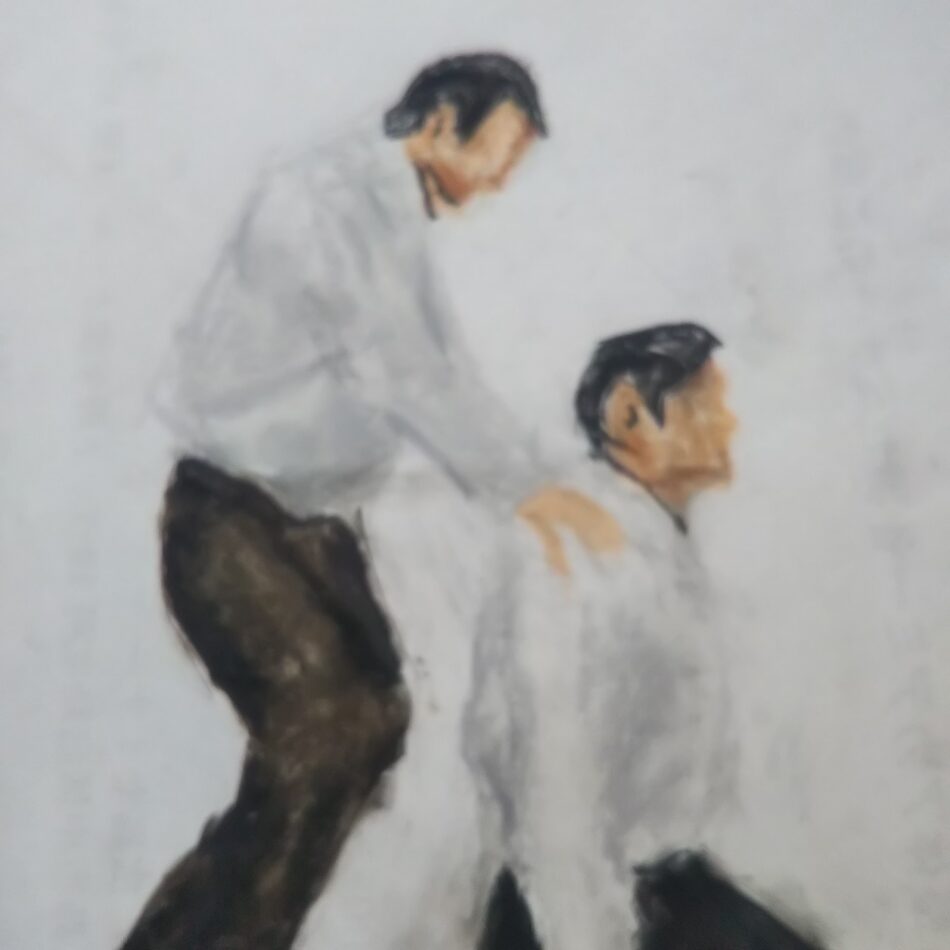
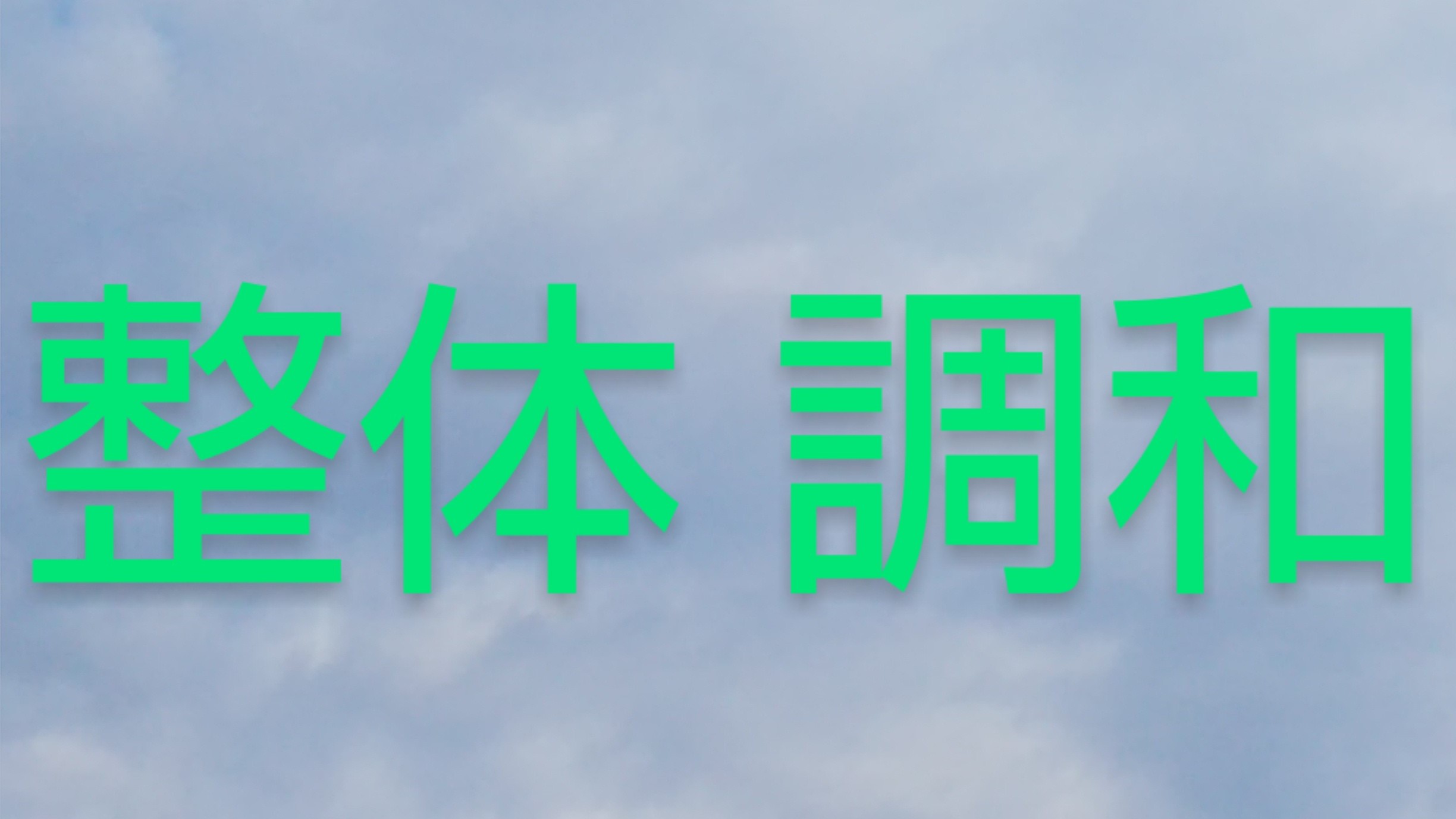



コメント