「暑さ寒さも彼岸まで」というように彼岸を過ぎたら暖かさが安定しますが、これから桜の花が咲くときまである意味では冬よりも身体が冷えます。
それは寒暖差と薄着が原因です。
昼は暖かくても夕方からは気温が下がり、明け方にはさらに気温が下がります。
春の陽気が満ちてくると、人々は薄着になります。
朝晩の寒暖差と薄着で冷える、桜が咲くときに頻繁に起きるので「花冷え」とつけられました。
服装を調整すること
面倒ですが、昼と夕方からは服装を調整しましょう。
夕方からシャツを1枚増やす、あるいは上着を羽織るといった工夫で冷えを防ぐことができます。
寝るときは、必ず靴下を履くことです。
素足で寝ると、明け方から気温が上がるときに足元から冷えが浸透します。
冷え以外のトラブルも多い時期
暑くもなく寒くもなく、過ごしやすい時期に入りました。
しかし、寒暖差によるトラブルが起きるので、ある意味で厄介です。
血管の膨張と伸縮が激しく、心臓へのストレスがかかります。
血圧が上がりやすく、心筋梗塞などが起きます。
心臓のトラブル以外にも小便が出にくい、頻尿になる、食欲が落ちる、肩がこる、このような症状も生じます。
「木の芽時」でも述べましたが、精神分裂と頭の異常も増えます
暖かくなれば、身体が弛み左の骨盤も開いていきます。
左の骨盤が開く体質の人は、脳に上がる血行が滞ることがあります。
左の骨盤を閉めて、脳に上がる血行を調整します。
小便が出にくい人や頻尿の人には泌尿器と関係する胸椎10番と腰椎3番を調整します。
食欲が落ちる人には右の骨盤を上げて消化器と関係する胸椎6番と8番と腰椎2番を調整します(器は右の骨盤と関係する)。
心臓のトラブルは、胸椎4番の左側を調整すると好転します。
脳の血行が滞る、小便が出にくい、食欲が落ちる、心臓のトラブルが起きる、これは個人の体質にもよります。
全ての人間に同じ症状が起きるわけではありません。
その人の体質によって、起きる症状が変わります。
冷えを感じるときは、踝まで湯に浸かる足湯が、食欲が落ちたときは膝まで湯に浸かる脚湯を推奨します。
イライラするから食べて発散することは、血糖値が上がるなどの問題があるので、健全ではありません。
屋外に出て、日光を浴びて軽い運動をすることがベストです。
適度な運動は、精神が安定します。
血圧が上がったときは、背骨をよく動かしましょう。
身体が弛めば、血圧は下がります。
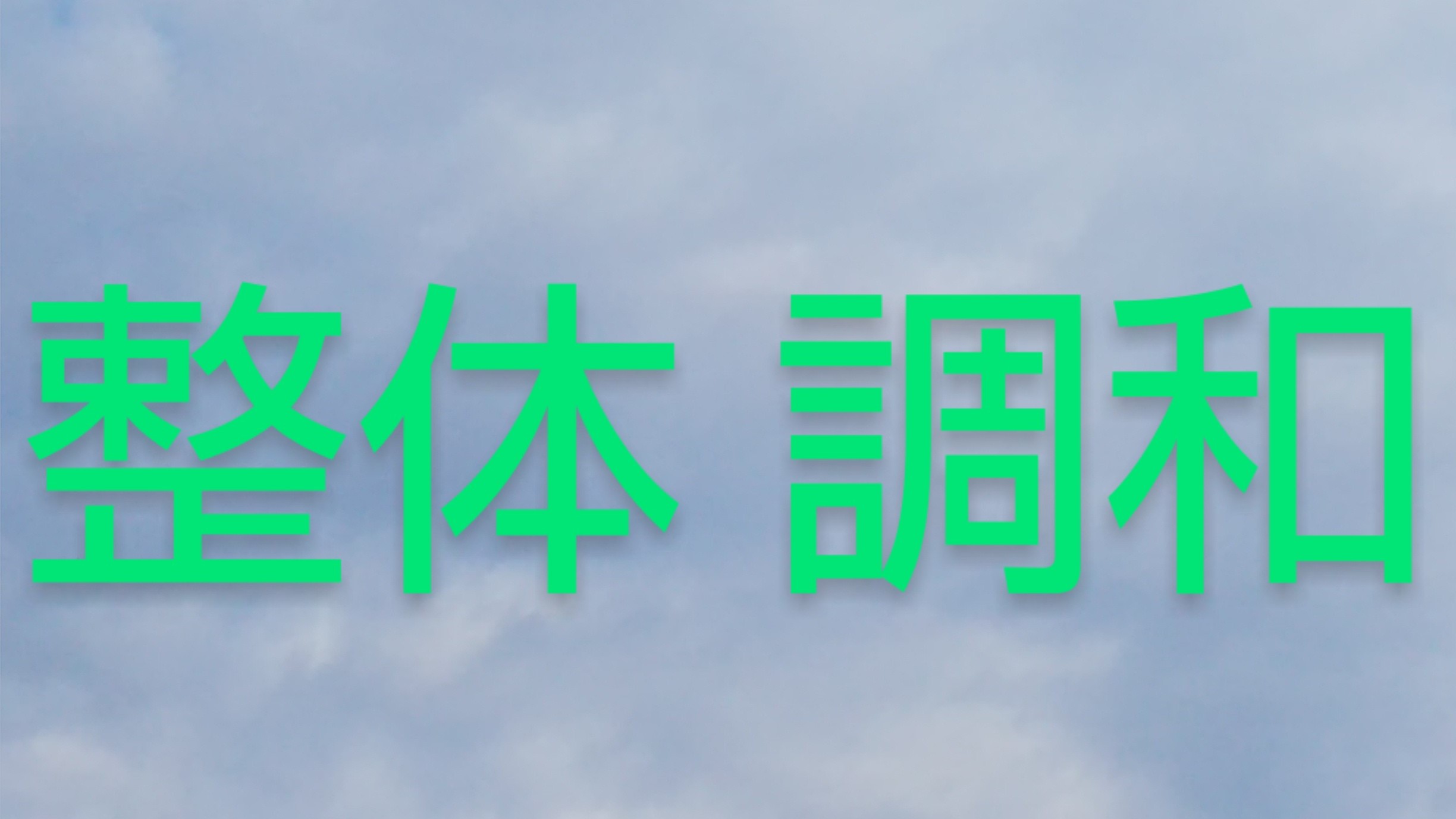



コメント