胸椎1番から12番まで
胸椎は頸椎に続く12個ある椎骨です。
胸椎には肋骨がついています。
11番と12番の肋骨は浮遊肋骨と言われ、前面の肋軟骨に付着していません。
不安定で折れやすい箇所です。
胸椎1番~3番
胸椎1番~3番の三側は目と器官に関係するので、1番~3番を一つにまとめています。
目が疲れると咳が出ることがあります。
胸椎1番~3番が目と器官に神経がつながっているからです。
胸椎1番は血圧と左二側は記憶力と関係します。
左の骨盤が開いて脳に上がる血行が悪くなれば、左二側が硬直します。
胸椎2番は肩が冷えたときに二側三側四側に硬直が現れ、肩こりを感じます。
リウマチや慢性気管支炎のときに調整する椎骨です。
胸椎3番は肺結核のとき一側か三側に刺激を与えると、喀血の引き金になります。
胸椎4番
左一側~三側は、心臓とつながっている神経が出ています。
左一側は心臓の迷走神経と食べた物の嚥下と二側は心臓の交感神経と関係します。
心臓麻痺が起きたときに一側を弾いて二側を押さえて一命を取りとめた例があります。
三側は、不整脈と左の骨盤を閉めるときに調整する箇所です。
右の三側は肝臓の収縮と関係します。
右の二側と四側は、腕の疲労を取るときに使う箇所です。
胸椎5番
呼吸器と発汗と水分の吸収と関係する椎骨です、
肺の機能が低下したときや風邪をひいたとき、硬直が現れます。
夏になっても汗が出ない人や水分の吸収が悪い人は、胸椎5番が硬直しています。
胸椎6番
三側は、腰椎2番三側と連動し、胃の収縮を活発にします。
胸椎7番
皮膚と泌尿器と関連する椎骨です。
左一側は脾臓と関係するため、虫刺されなど血管に異物が入ったときに調整します。
脾臓と関係するため、免疫力を高めるときは必ず調整します。
胸椎8番
交感神経が緊張したときや免疫力が低下したときに弾力がなくなり左側が硬直します。
冷えたときにこの椎骨が飛び出すので、この椎骨に弾力をつけることで体温が上がります。
左側は胃腸と膵臓と神経がつながっています。
胸椎9番
右三側は肝臓と左二側は脳に上がる血行と関係します。
肝臓とうつ病や認知などで調整する椎骨です。
胸椎10番
左三側は腎臓と右三側は副腎と関係する椎骨です。
腎機能が低下したとき、副腎の機能を高めたいときは、必ずこの椎骨を長y制します。
胸椎11番
下半身が冷えて腰痛が起きたとき左一側にシコリができます。
このシコリを弛めることで冷えからくる腰痛が和らぎます。
胸椎12番
左三側は左の骨盤が開いているとき、右三側は右の骨盤が下がっているときに調整すると、弾力が戻ります。
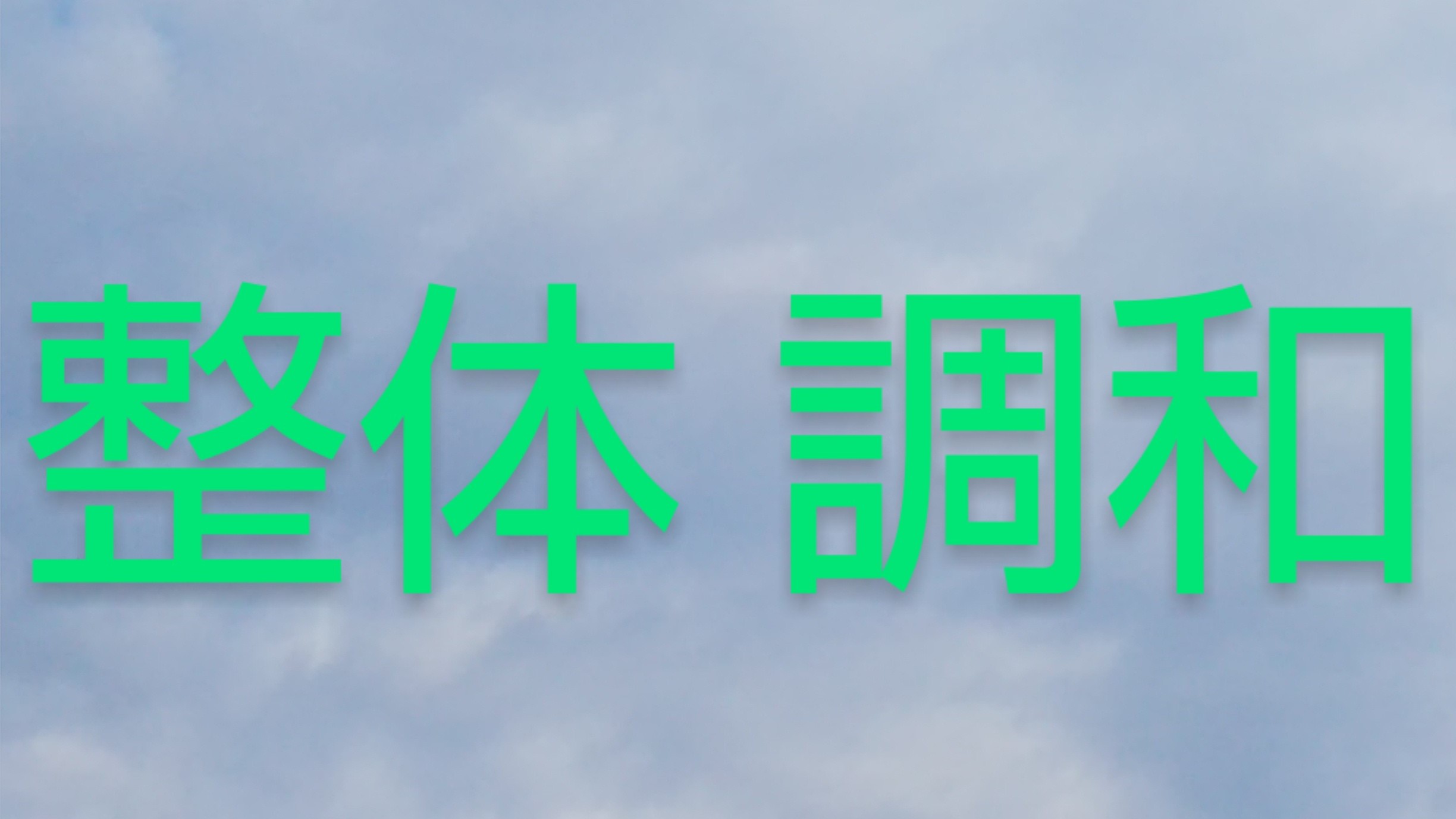



コメント