2月3日の立春から暦の上では春の始まりです。
春の始まりだと言っても、冬型の気圧配置のため全国各地で雪が積もっています。
この寒波が過ぎたら、暖かくなったり寒くなったりと寒暖差が大きい時期に入ります。
この寒暖差があるときに風邪をひく人が居るのですが、ご存じですか?
なぜ寒暖差が大きい季節の変わり目に風邪をひくのか?
これからお話しします。
風邪をひくのは春の身体に変化できないから
冬は体温を維持するため、身体は引き締まって、皮下脂肪をつけて毛穴を閉じています。
1年で最も身体が引き締まっているのが12~1月です。
しかし、クリスマス辺りから少しずつ春の身体に変わる準備を始めます。
矛盾しているように思われるかもしれませんが、クリスマスから1月にかけては後頭部が弛みます。
2月から肩甲骨が弛み、3月から骨盤が弛みます。
2~3月は春の陽気を感じるくらい温かい日が来ます。
この暖かい日に身体は弛めようとしますが、冬の寒さに戻る日が来ると身体は上手く弛みません。
上手く弛まないときに風邪をひいて熱を出す人が居ます。
熱を出すことで弛めようとしているのです。
風邪は正常なもの
正月明けの風邪でも書いたように季節の変わり目にひく風邪も異常ではありません。
熱を出すことで身体を弛めようとしているので、自然に経過させるようにするのがベストです。
経過した後は、身体がスッキリします。
整体では、後頭部・肩甲骨・骨盤に動きをつける調整をします。
風邪に関係する胸椎5番もこわばっていたら、弛めます。
このような調整で早く経過します。
季節の変わり目は、風邪をひくことだけではなく、花粉症になったりイライラししたりするようなことが起きます。
それらの話も近々いたします。
寒い時期でも変化するのは、人間だけではありません。
冬眠している動物は外に出る準備を植物も芽を出す準備をしています。
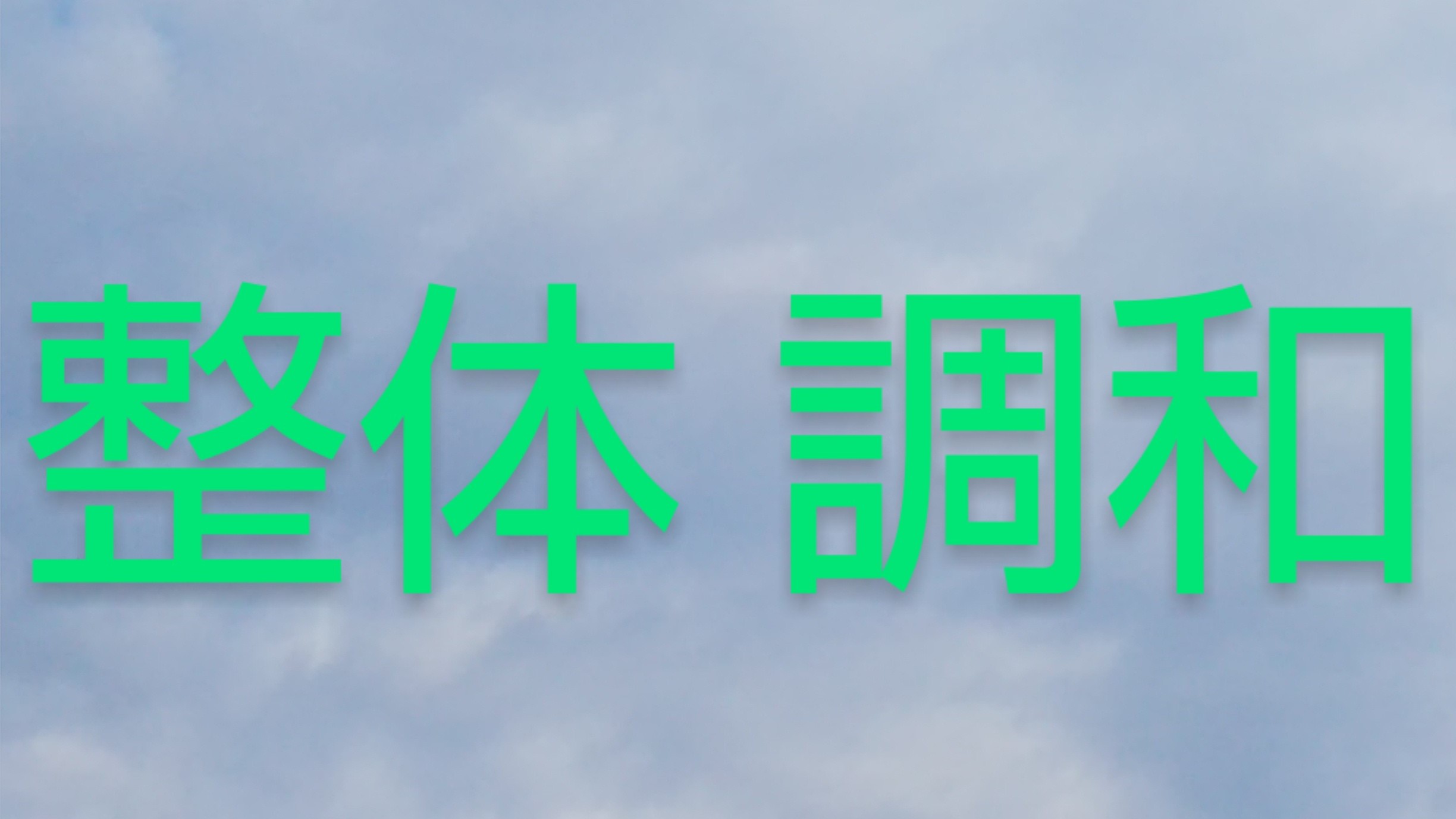



コメント