水分を摂って秋から冬を快適に過ごす
10月の下旬にさしかかれば、空気の乾燥が進んでいます。
これから湿度が30%くらいまで落ち込みます。
梅雨の時期は80%以上なので、半分以下ということです。
人間の皮膚からも少しずつ水分が蒸発し、乾燥によるトラブルも増えていきます。
乾燥によるトラブルを避けるためには、定期的に水分を摂るようにしましょう。
がぶがぶ飲んだら小便として出ていくので、ちびりちびりと飲むことです。
秋から初冬にかけては、温かくて汁気がある鍋物に味噌汁にスープなどを積極的に摂れば、身体が水分をたくさん吸収します。
乾燥によるトラブルとは?
唇と口の中が乾く、痰が絡む、肌が痒い、小便が近い、小便の色が濃い、浮腫む、水分不足からこういった症状が起きます。
浮腫みと頻尿は水分の摂りすぎのように思われますが、体内の水分を出し惜しんだための現象です。
頻尿も水の飲みすぎではなく、身体の乾きから起きています。
また、水分が不足することによって、身体もこわばり、腰が痛い、肩がこる、神経痛のような症状も起きやすくなります。
秋から冬にかけては、夏のように喉が渇いたから水を飲みたいという感触がありません。
つい水分の補給をしなかったばかりに、乾燥のトラブルが起きます。
水分の吸収が悪いときの調整
乾燥が進めば、から咳が出て胸椎5番と10番が飛び出し、腰椎3番が捻じれます。
ここまできたら、慌てて水分を摂ろうとしても、身体は上手く水分を吸収できません。
整体では足の3~4趾を広げて、左の骨盤を締め、胸椎5番と10番に動きをつけます。
そうすることで、水分の吸収が上手くいくようになります。
個人では、風呂に入ったときにチビチビ水を飲むことを推奨します。
湯船に肩まで浸かり、すぐに冷たい水を口に含みます。
2分ほど経てば、口の中がネバネバするので、吐き出します。
2口目からチビチビと飲みます。
風呂の湯は、少し熱い目にするのがコツです。
そうすることで、体内が潤います。
※足の3~4趾間を広げる調整は、冷えを解消するときに使いますが、乾燥したときにも使います。
空気の乾燥から風邪をひくことがあります。
気温が下がって冷えたからではなく、乾燥しているから風邪をひくのです。
咳が出て熱が出ます。
熱が出たときというのは、最も水分の吸収が上手くいくときです。
熱が出たときに水を飲めば、水分がよく摂りこまれ、身体はスッキリします。
間違っても解熱剤で下げることは、しないようにしましょう!!
感染症の関係から熱が出ることは恐ろしいことだと報道されていますが、熱が出るって正常なことです。
整体の世界では、風邪と発熱は病気や異常だとは考えていません。
身体を正常な状態に戻すための機能だと考えています。
風邪と感染症に関しては、今後「風邪と感染症」というカテゴリーを作って書いていきます。
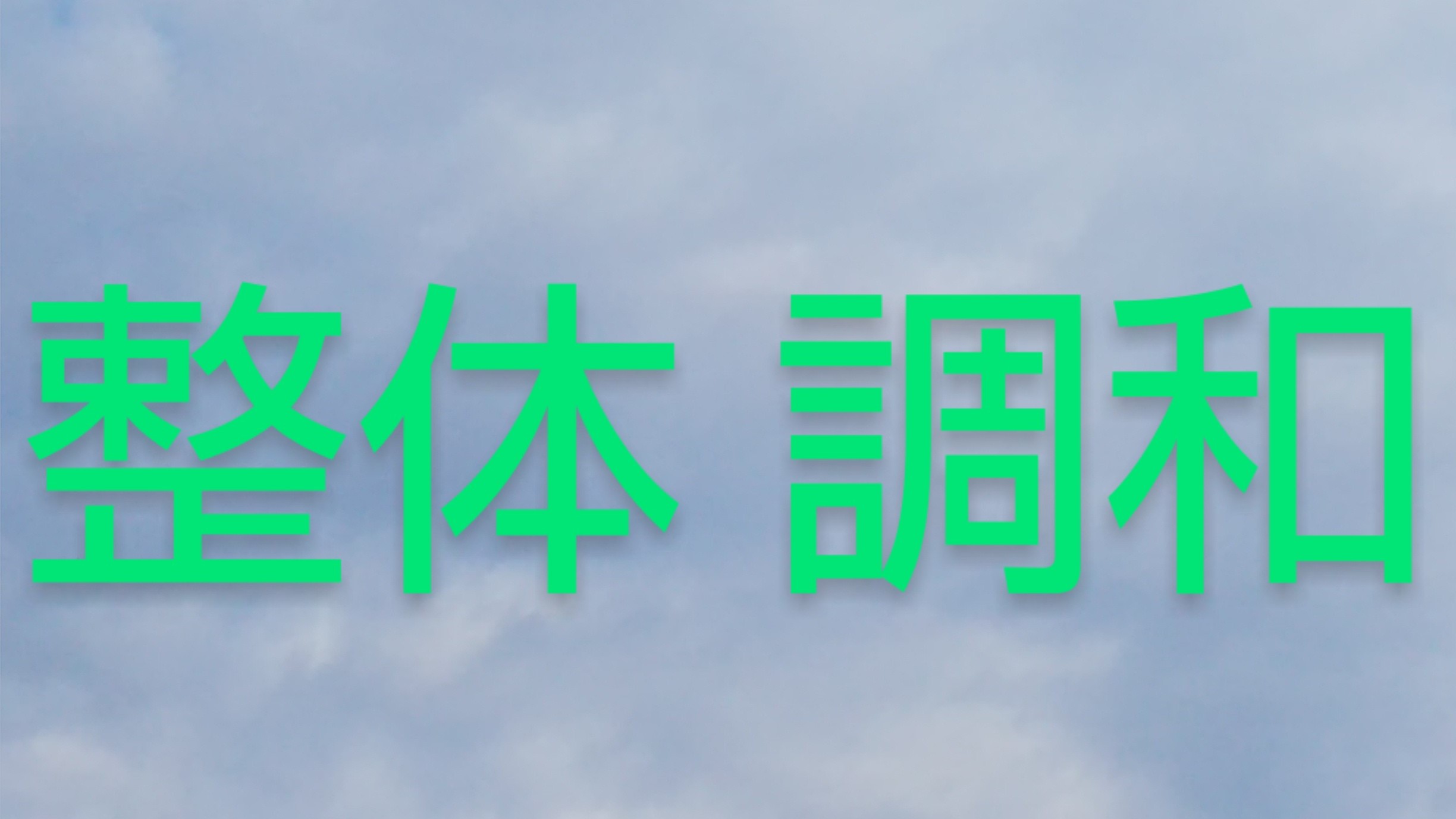



コメント